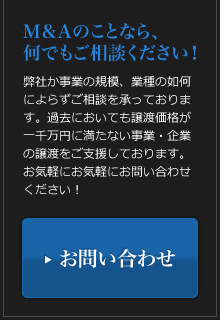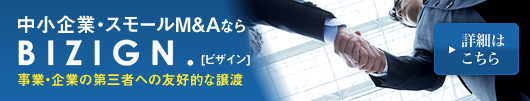‘こんなときM&A’ カテゴリーのアーカイブ
皆様、こんにちわ。
本日は、
競合大手(自社よりも規模の大きい競合・同業者)の傘下に自ら入るというM&Aによる売却についてお話させていただきます。
「M&Aにて、売却」
というと、何となくネガティブを印象を抱かれると思います。
しかし、ここ数年、自ら会社を売却して、大手の傘下に入りたいというご相談が確実に増えております。
そして、その理由は、概ね一つに集約されます。
それは、「先行き不安」です。
マクロ的な環境を見ても周知の通り、日本は、低成長、少子高齢化などにより、市場のパイの広がり
は多くの産業では期待できない環境にあります。そのような環境下で、市場のパイを獲得しようとする場合
・新市場を開拓する(例:海外市場へ出る)
・既存市場を競合から奪う
が考えられます。
生き残りを図ることについては、大手も中小も違いはないので、大手といえども、なりふり構わず市場奪取の攻勢をかけてくる。
多くの産業の中小企業は、そこと戦うことになります。
ミクロ的、つまり、こうした攻勢が肌で感じられるまでには、若干のタイムラグがあるものなのですが、それが、現場でも肌で感じられるようになったのがここ数年のことであり、これこそが、「先行き不安」の主要な原因だと考えられます。
次に、
「先行き不安で、大手の傘下に入りたい」とご希望される方々のM&Aに対するご希望(売却時に買い手側に提示する希望)についても、特徴がありますので、ご紹介させていただきます。
取引先、従業員、販売先の承継は、どのM&Aでも共通なのですが、これ以外に、
売り手の社長も、大手傘下で、相応のポジション(報酬含む)をいただいて、引続き同事業(会社)を、大手傘下のもとで代表者としてのキャッシュマネジメントからは開放され状態で、推進していきたいとのご希望が、このM&Aの特徴になります。(簡単にいうと、資金繰り・保証債務からは開放されて、一幹部として、事業に集中したいということです。)
最後に、
このようなM&Aを、我々M&Aアドバイザーの視点から見た場合の特徴をご紹介させていただきます。
このようなM&Aの場合我々は、以下のようかことに留意をして進めて参ります。
・売り手様に意中の大手がある場合、その大手への慎重なアプローチ
(意中の相手がいない場合、その調査・ご提案)
・株式譲渡、第三者割当増資、或は、株式交換など状況に応じたスキームの検討
・譲渡後の売り手社長の大手でのポジションと報酬などの交渉
・大手傘下での業績に応じた退職金・報奨金などの交渉
本日は、
競合大手(自社よりも規模の大きい競合・同業者)の傘下に自ら入るというM&Aによる売却についてお話させていただきました。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
本日は、上場会社2社をご訪問。業種は違えど、弊社へのご要望は同じ。
当然上記2社様、弊社以外にも大手、準大手のM&Aアドバイザー会社とお付き合いはあるのですが、紹介される案件の規模は大き過ぎるというこで、弊社にお声掛けいただきました。
M&Aは希望の案件を待っているだけでは、ほぼ取得することは不可能です。”待ち”ではない、取得方法などご説明させていただきました。
弊社に売却のご相談をいただく多くの方が、規模が小さいのですが、M&Aで売却の可能性はあるのでしょうか?或いは他社では、規模が小さく断られたというお悩みをお持ちで来られます。
弊社過去の実績で、小さいものは、年間売上数百万円という案件、譲渡代金200万円という案件の事例をご説明させて頂いております。
勿論、売上規模、利益規模は重要なファクターではあるものの、買い手様からみて、取得したいという魅力があれば、規模の大小に関係なく、譲渡することが可能です。
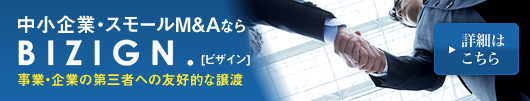
いまそこにあるMBO
(たまには長文投稿)
MBOとはマネジメントバイアウトの略。
株主から会社の所有権を経営陣が買い取ることです。
??何となくイメージが沸かないかもしれませんね。
通常ニュースで出てくるMBOとは、上場企業の上場されている
株式を経営陣がファンド・銀行団の力を借りて、市場で買い付けで上場廃止にする的なことですね。
もっと??かもしれませんね。
もっと簡単に、身近な事例で説明すると、
自分が株式100%(親族で100%或いは100%近く)もっていて自分が代表取締役でもある会社を従業員(役員)に譲ることです。
私の生業は御存知の通り、中小企業(特に小規模)のM&Aアドバイザーです。
私のようなM&Aアドバイザーは通常、会社・事業・部門を(親族内に承継者が以内場合)第三者に承継するお手伝いしています。
しかし、実は、よくよく売却希望の会社・事業を知れば知るほど、外部の第三者でなく、役員などの経営幹部に譲渡するのがベストであるという事例が多々あります。
しかし、しかしです。
残念ながら、今までサラリーマンだった経営幹部には資力がありません。
社長の株式を買い取るお金がないのです。
経営幹部に譲渡するのがその会社・事業にとってもっともフィットする、しかし、買い取る資力がないのです。
だったら、その資力を提供(出資・融資)してあげる事業があるかと言えば、冒頭に記述した大企業の場合(ファンド、銀行団)以外はないのが現状です。
実にもったいない機会損出だと思います。
もっと身近なMBOファイナンスを支援する事業を是非立ち上げて欲しい。
特に地域金融機関には。
私に資力があれば、是非やってみたい事業である。
中小企業のM&Aアドバイザーとして活動して7年。
この中小企業の身近なMBOファイナンスがどの金融機関でも
相談できるようになることは非常に意義があると思う。
何せ、後継者がいないというだけで、年間7万社が清算している。
親族内承継も年々減っている。
MBOで中小企業のゴーイングコンサーンを支援することが当たり前になる世の中になることを期待して止まない。
最後になりますが、事業は、その事業に熱意ある人が承継するのが事業自身にとっても、従業員はじめステークホルダーにとっても、もっともハッピー。(さして情熱のない親族、株だけもっていてる社長ではアンハッピー)
そこにあるMBO支援。誰か一緒に始めませんか?w
【歯科医院の買収希望(買いたい!)情報です!】
福岡市並びにその近隣市町村にて、歯科医院の買収希望情報(買いたい!というご希望)があります。
大手医療法人様が歯科医院を拡充するためです。
原則的に、歯科医院の先生には継続して医院長として継続してもらうことが条件です。
売上、借入などの財務状況なども限度はありますが、柔軟に対応する予定です。
売却を検討の方、情報のお持ちの方お問い合わせくださいませ。
http://www.bizign.jp/order
最近増えて来た、お問合せが、現在は、サラリーマンとして勤めてる個人のお客様からの買収希望のお問合せ。独立或いは副業を新規事業でやるよりは、収益、リスク、問題点、良い点など全て最初に把握できるM&Aによる取得で、スタートを切ろうという、お考えです。
一時期、飲食関係などは、居抜き譲渡物件を取得して独立するというものが流行りましたが、M&Aの方が断然向いています。取得したその日からもう売上があがりますし、人(スタッフ)もいる訳です。即売上を確保しつつ、徐々に予め分かっている問題点の改善を計っていける訳です。
【M&A相談のタイミングが明暗を分ける!】
土日にも関わらず、ネット経由でM&Aの御相談が2件。その他にも、お知り合いがM&Aを考えているということで、弊社をご紹介いただきました。感謝です。いずれも、業績不振系の売り案件ですが、まだ十分に間に合います。ご期待に添えるように精進させていただきます。
M&Aでも事業再生でも御相談いただいたときに、もっとも多いのが、”遅すぎる”というもの。これにはなかなか打ち手はありません。が、早めのご相談は、業績不振系であったも、色々な打ち手を講じることができます。
御相談は是非お早めに、ご遠慮なくしてください!
低成長且つ不振に喘ぐ日本経済。
生き残りの活路は、成長著しい新興国。。。という文字は、毎日、どこかで目にします。
勿論、総論では間違っていません。しかし、誰でも、どんな方法でも成功する訳でないことはちょっと考えると分かります。
それを裏付けるように、新興市場からの撤退や、新興市場での将来的な不安、利益確定の為、新興国での事業をローカルな企業などに売却する動きも目立ってきています。
新興国への進出が、低成長且つ不振に喘ぐ日本経済、引いては、自社の将来性成長性への不安をブレークするための手法であるなら、もう一つ、別の戦略も残されています。このもう一つの戦略を着々と進める小規模・中小企業が増えています。
それは、IN_INのM&A。
一概には言えませんが、取引先からの要請と指導による新興国市場への進出は別として、国内がだめ→新興国だ!的な短絡的な発想による進出に、比べるとこのIN_INのM&Aは遥かにリスクが小さいと思います。
では、なぜ、リスクが低いであろう、国内のM&Aではなく、新興国への進出をするのか?
それには、M&Aに対する認知と文化が大きく影響しているように思います。
ちょっと、考えてみてください。
中小企業の新興国市場セミナー的なものと
中小企業の成長戦略としてのM&Aセミナー的なものと
どちらが多く開催されている印象をお持ちですか?
恐らくは、中小企業の新興国市場セミナーの方だと思います。
認知不足とM&Aが一般化していない証左ではないでしょうか?
ここで言いたいのは、
新興国市場への進出は特別な場合を除いて、リスキが高く、決して新興国市場=成功ではないということと、低成長の市場でもM&Aという成長戦略があるということ(こちらも勿論リスクは伴い、成功を保証するものではありません)。
そして、小規模・中小企業の中には、新興国市場へ!という風潮に踊らられることなく、着々と国内のM&Aで成長を果たしている会社があるということです。
小規模、中小企業同士の国内のM&A、(仲間同士による)合併などによる成長戦略もお考えてみてはいかがでしょうか?
企業の再生を図る手法としては、民事再生法や会社更生法などの手続による法的整理、あるいは私的整理の手続をとるなどが考えられます。
それらの手続の開始前に、事前に再生をサポートするスポンサーや事業譲渡先、そのスキームを決定たうえで手続を進めることを「プレパッケージ型」と呼びます。
このプレパッケージ型(のM&A)は、再生企業そして、スポンサー企業の両方にとって大きなメリットがあります。
再生企業のメリット:
整理の手続等に入ると、周囲に与えるマイナスイメージは事業に更なるダメージを与えます。販売先や仕入先、従業員などのへの悪影響が生じ、再生へ向けたの事業基盤が大きく損なわれる可能性があります。
。プレパッケージ型で事前にスポンサーの存在が再建計画に織り込まれていれば、債権者の合意を得られやすく、事業価値の劣化・毀損を最小限に食い止めることができます。
スポンサーのメリット:
時間を買うという通常のM&Aのメリットに加えて、再生会社の事業、財務の透明性が高い、引き継ぐ負債がないか、整理前と比べると極端にすくないというメリットがあります。更に、取引先や仕入れ先、従業員の再生へ向けたモチベーションと同じ事を繰り返さないという良い意味での危機感が組織の中に芽生えます。
M&Aをその重要な経営戦略と位置づけている会社の場合、むしろ、私的にしろ、法的にしろこのプレパッケージ型のM&Aを好む会社もあります。
弊社でも現在、プレパッケージ型のM&A(加えて事業承継としてのM&Aを加わっています。)、そして、民事再生申立後のスポンサー探しのM&A案件の2つが動いています。
プレパッケージ型の事業再生(M&A)。是非その存在と活用の可能性と意義を知っていただけたらと思います。そして、是非お気軽にご相談ください。弁護士の先生からのご相談もお待ちしております。
M&Aにおいて、見切り・損切りは一級の戦略である場合があります。
例えば、業種は何でも良いのですが、店舗を急拡大(或いは堅調に拡大)してきたとします。
ところが、コントロールできない外部環境の変化によって、赤字店舗が増えてきたとします。
選択は4つ。
①外部環境の変化を打ち消す対策をとる。
②外部環境が好転するまで耐える。
③①と②の合わせ技
④見切り・損切り
外部環境の好転を待つ体力があるなら、①乃至③を選択することは良いと思います。
しかし、その体力がないにもかかわらず、最後に取られるのが④。
これが問題なのです。
店舗の拡大と全く同様に、店舗の縮小、売却も立派な戦略であるにもかかわらずです。
④の判断が遅れた場合、全体に負の連鎖に覆われ、再起不能(或いは相当に再起まで時間がかかる)状態になりかねません。
④をいち早く判断できた場合は、黒字店舗だけで再起を計ることが可能になります。減収にはなりますが、利益は確保できる状態で食い止めることが可能です。
機が来たら、また前回同様拡大すればいいだけのことです。
④をM&Aによる売却で行った場合は、従業員の雇用も確保されます。
絶対に、世間体やサンクコストの呪縛で判断を遅らせてはいけません。
拡大も縮小も同じ舞台の立派な堂々とした戦略ということを忘れずに!