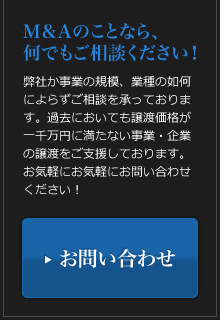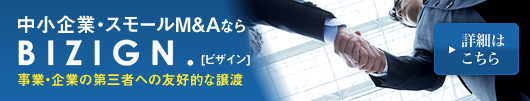企業の目的は、持続可能な長期間に渡る利益をあげること。顧客満足度も、ステークホルダー満足度も、従業員満足度も、社会貢献も、この利益がないとできないこと。長期間に渡り持続可能は利益を上げるということは、顧客が認識できて、且つそれが顧客のベネフィットに繋がる他社との”違い”を作ること。
この”違い”が曲者なんです。
時間があれば解決できる(他社が模倣できる)違い、計ることができる違いは、往々にして、自社で思っているほど、長期間に渡り持続可能に貢献しません。
時間があれば解決できる(他社が模倣できる)違い、計ることができる違いしかどうしてもないビジネスの場合、その取るべき戦略は、スプリンクラー方式によって一気に市場を取り、先行者利益を取ること。
本日のクライアント様のご相談は、上記のような新規事業をデット・ファイナンスでやるか、エクイティ・ファイナンスでやるかというもの。私は勿論エクイティでやることを進言しました(その他ここでは書き切れない色々な情報の加味の上ですよ。)。
エクイティ・ファイナンスとは、金融機関の融資ではなく、出資を得るという資本取引です。資本を受入れるということのデメリットは、銀行の融資に比べるとリクスもコストも大きいのですが、圧倒的なメリットは、一気に事業を拡大できることです。
本ケースの場合の一般的なスキームは、新設分割により、新規事業を新会社に分割します。その上で、増資を行い、出資者に引き受けてもらう、新株引受になります。
[欠損金]
会社分割において合併類似適格分割型分割に該当しない場合には、繰越欠損金を引き継ぐことはできません。M&Aで合併類似適格分割型分割に該当することは稀なケースです。
[法人住民税(均等割)と事業税(資本割)]
会社分割により、承継会社の資本金等の額が大きく増加することに伴い、法人住民税の均等割と事業税の資本割の負担が増加するケースがあるので注意が必要です。
[不動産取得税]
会社分割により承継会社が不動産を取得した場合は不動産取得税が課税されますが、一定の要件を満たした場合は、不動産取得税は非課税となります。
[単独新設分割(分社型分割)]
単独新設分割の場合、分割会社と継承会社は親子関係となるため共通支配下の取引に準じた処理となり、分割資産・負債は全て帳簿価格で移転します。ただし、分割後速やかに継承会社株式を第三者に譲渡する場合は、「取得」(パーチェス法)として時価で継承することに注意が必要です。
継承会社では利益準備金およびその他利益剰余金を引き継ぐことができないことに注意が必要です。以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)参照

[吸収分割(分社型分割)]
吸収分割の場合、分割会社の取得する承継会社株式が、分割会社にとって子会社株式(承継会社が分割会社の連結子会社)となるか、関連会社株式(承継会社が分割会社の持分法適用会社)となるか、あるいはその他の有価証券になるかによって会計処理が違います。
(1)子会社株式に該当する場合
この場合は「逆取得」に該当するため、承継会社は帳簿価格にて資産・負債を引き継ぎます。一方、分割会社は移転事業に関する投資が継続していると考え、資産と負債の帳簿価格の差額が子会社株式となり、分割に伴う移転損益は発生しません。以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)参照

(2)関連会社株式に該当する場合
この場合は、「取得」に該当するため、承継会社は時価にて資産・負債を引き継ぐことになります。一方、分割会社は移転事業に関する投資が継続していると考え、資産と負債の帳簿価格の差額が子会社株式となり、分割に伴う移転損益は発生しません。以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)参照

(3)その他有価証券に該当する場合
この場合は、「取得」に該当するため、承継会社は時価にて資産・負債を引き継ぐことになります。一方、分割会社は移転事業に関する投資が継続していないと考え、対価として受け取った承継会社株式は移転した事業に係る時価または承継会社株式の時価のうち、より信頼性をもって測定可能な時価に基づいて算定します。そのため分割に伴う移転損益が発生することになります。以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)参照

[分割対象物]
分割対象は、会社法において「事業に関して有する権利義務の全部または一部」となっており、事業性の要件が不要となっています。したがって、事業譲渡と違い事業用資産の一部のみの分割も認められると解釈することが可能です。分割対象物の明細は、分割計画書等に記載され、株主総会での承認を受ける必要があります。
[簡易分割]
分割会社は、分割する資産の帳簿価額が分割会社の総資産の5分の1以下である場合には簡易分割に該当し、株主総会決議を省略することが可能です。
継承会社は、交付する財産の額が、純資産額の5分の1以下である場合には、簡易分割に該当し、株主総会決議を省略することが可能です。ただし、反対株主が継承会社の総株式数の6分の1を超えた場合や継承会社が譲渡制限会社であり譲渡制限株式を割り当てる場合は、株主総会を省略することはできません。
[略式分割]
親会社、子会社間の吸収分割において、親会社が子会社の90%以上の議決権を保有している場合、子会社側の株主総会決議を省略することができます。ただし、子会社が継承会社の場合で、子会社が譲渡制限株式を交付する場合は株主総会を省略することはできません。ただし完全子会社が完全親会社に無対価で資産などを分割する場合は、完全子会社側での株主総会決議は省略することが可能です。
[債務履行見込み]
会社分割の事前開示事項の1つに「分割後の分割会社・継承会社における債務の履行に関する事項」があります。債務履行の見込みは、本来キャッシュフローの問題であり、債務超過であっても債務履行の見込みがないということではありません。したがってキャッシュフローの観点から債務の履行の見込みがあることを明らかにする必要があります。
[債権者保護手続の省略(分割会社)]
分割会社が重畳的に債務を引き受けて、分割会社の株主に剰余金の配当などを行わない場合は、債権者には特段の不利益はないと考えられるため、分割会社における債権者保護手続を省略することが可能です。
一方、継承会社における債権者保護手続は、省略することができません。
[財産・契約上の地位の移転]
会社分割は、合併と同じく、権利義務の承継は包括承継とされ、個別の財産や権利義務につき個別の移転行為は必要ありません。ただし、権利の移転について第三者への対抗要件の具備を要するものについては、手続きが必要となりますので注意が必要です。
会社分割では労働継承法に基づき、分割対象事業に主として従事している労働者に関して、分割前後で労働条件が維持されることを前提として、労働者の同意を得ず当然に労働契約を継承されることができます。ただし、労働者保護の手続きが制定されており、その手続きを踏んでいな場合、分割無効とされる可能性があるため注意が必要です。
以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)は、会社分割の一般的な手続きで、基本的な流れは合併と同じです。会社分割固有の手続きとして労働継承法上の一連の手続きが加わります。また一定の要件を満たせば、債権者保護手続きは不要です。

メリット:
(1)買い手企業は対価として新株を発行すればよく、買収資金(現金)が不要
。
(2)包括継承のため、事業譲渡と比べて契約関係の移転手続きがシンプル
。
(3)転籍させる従業員から個別に同意を得る必要がない
。
(4)買い手企業は、買い手内に被分割事業を取り込むので、一気に経営統合を実現でき、ナジーを早期に実現し易い。
デメリット:
(1)買い手企業が上場企業の場合、新たに株を発行するため1株当たりの利益が減少し株価下落のリスクがある
。
(2)買収対象企業の株主が買い手企業の株主となるため、買い手企業の株主構成が変化してしまう
(既存株主の希薄化)。
(3)一気に内部にとり込みため、統合での負荷が大きい。
会社分割には、新設分割と吸収分割の二種類があります。新設分割とは、1または2以上の会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割により新たに設立される会社に継承させることをいいます。吸収分割とは、1または2以上の会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割し、他の既存の会社に継承させることをいいます。
また、会社分割には、分割の対価を分割会社の株主が受け取る分割型分割と分割の対価を分割会社自身が受け取る分社型分割があります。以上を総合すると、会社分割の類型は以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)の2種4通りとなります。

企業組織再編の方法の一つで、既存の会社の部門の全部または一部を、他の会社に包括的に継承させることにより会社を分割すること。不採算部門を切り離したり、あるいは成長部門を子会社として切り離すなどして、経営効率を高めることができる。
会社分割が制度として導入されたのは最近のことで、2001年の商法改正による。それ以前の会社分割には事業譲渡(当時は営業譲渡と呼称)のスキームを使用していたが、商法改正以降はこのスキームが使用されることが多い。会社分割に特化した制度であるため、事業譲渡による分割スキームと比較して分割プロセスが簡素かつ明確になっている点に両者の差異がある。