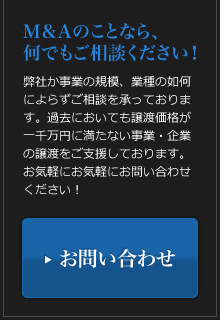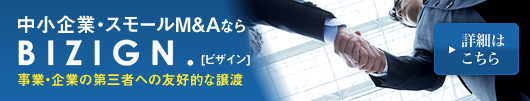[繰越欠損金]
適格合併に該当する場合は、基本的に消滅会社の繰越欠損金を引き継ぐことが可能です。
以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)、繰越欠損金の引き継ぎ判定をご覧ください。

【みなし共同事業要件】

※(1)~(3)を満たすか(1)および(4)を満たせばよい。
[特定資産に係る譲渡等損失の損金不算入]
特定資本関係発生後まもなく合併を行う場合、存続会社が所有し、もしくは消滅会社から引き継いだ資産の譲渡等損失の損金算入が制限される場合があります。以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)参照してください。

合併における最も基本的な形として、取得による会計処理は以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)の通りです。消滅会社の資産・負債を時価で受け入れることがポイントになります。
【例】
消滅会社の資産 簿価500,時価700
消滅会社の負債 簿価200,時価200
合併契約書で定めた増加資本の内訳 資本金200,資本準備金300
存続会社の新発行額(時価)500

[簡易合併]
合併により存続する会社が、対価として相手方に交付する財産の金額が、合併により存続する会社の純資産額の5分の1以下である場合に簡易合併に該当し、株主総会での合併の承認を省略することができます。
ただし、合併に反対する株主が存続会社の総株式数の6分の1を超えた場合や存続会社が譲渡制限会社であり譲渡制限株式を割り当てる場合は株主総会を省略することはできません。
[略式合併]
親会社と子会社間の合併においては、親会社が子会社株式の90%以上の議決権を有している場合、子会社側の株主総会決議を省略することができます。ただし、消滅会社(子会社)が公開会社であり、かつ種類株式発行会社ではない場合において、合併対価の全部または一部が存続会社の譲渡制限株式である場合は、略式合併は認められません。また子会社が存続会社で、存続会社の譲渡制限株式を割り当てる場合、子会社が非公開会社の場合には略式合併に該当しません。
[債権者保護手続き]
存続会社及び消滅会社はともに、債権者保護手続きとして、官報への公告及び知れている債権者に対する個別の催告を行わなければなりません。この手続きは、簡易合併や略式合併の場合にも省略することはできませんので注意が必要です。
合併に関する一般的な手続きは以下(木俣貴光「企業買収の実務プロセス」 中央経済社)の通りです。

合併のメリット:
(1)合併当事会社が一社になるため、合併後の統合効果を早めることが可能である。
(2)合併対価が株式であれば、買い手企業は資金調達せずに(現金を拠出することなく)買収することができる。
合併のデメリット:
(1)統合により発生する諸活動が大きく本業への営業が懸念される。
(2)合併比率によっては、買い手企業の株主の持ち分比率が希薄化し、株価に悪影響を与える可能性がある。
合併とは、複数の会社が一つになる組織再編行為のことをいいます。合併には、すべての合併当事会社の全てが解散して合併により新会社を設立する新設合併と、合併当事会社のうち1社が存続して他の当事会社が消滅する吸収合併があります。
複数の会社が法的な手続を経て、一つの企業に集約すること。
一方の会社が他方の会社の権利義務を承継する吸収合併と、複数の会社が会社を新設してそこに権利義務を承継させる新設合併の二種類がある。後者の場合、新しい定款の作成手続きが複雑になり、費用もかかるため吸収合併が多くの場合用いられる。また、1998年の関連法改正によって純粋持株会社の設立が可能になって以降、株式移転等で持株会社を設立し、持株会社にぶら下げる形で企業を吸収統合するケースが増えている。
ちなみに合併される会社の事業規模や知名度が同程度の場合は対等合併、大きな差がある場合には吸収合併と呼ぶ場合があるが、それらは社会的な慣用表現に過ぎず、法的には両者共に吸収合併である。